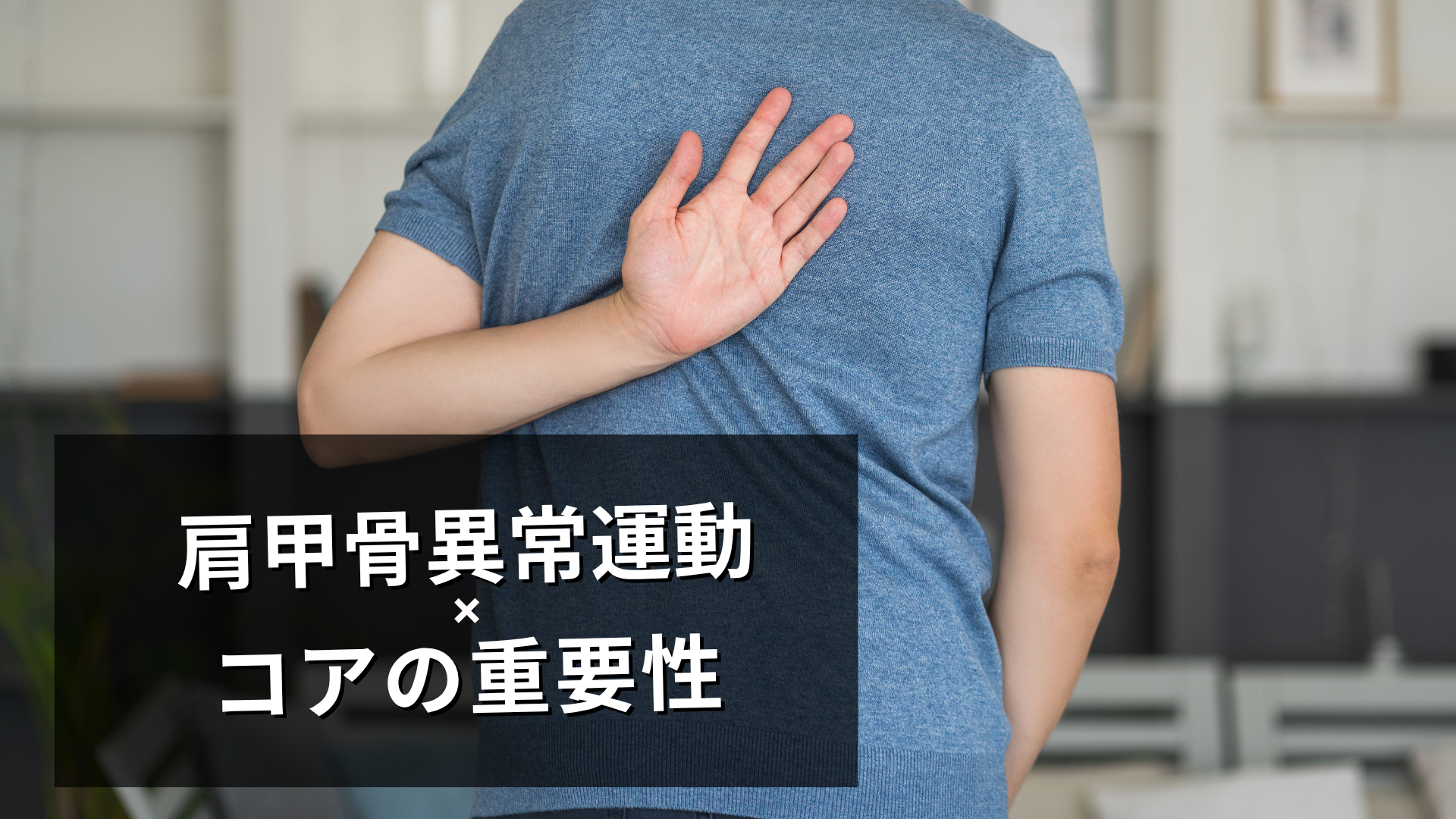
はじめに:肩甲骨異常運動の治療、なぜ「体幹」に目を向けるべきなのか?
こんにちは、小林龍樹です。 肩関節の痛みを訴える患者さんの多くに見られる肩甲骨異常運動(Scapular Dyskinesia: SD)。その治療として、私たちは前鋸筋や僧帽筋下部・中部線維の選択的な促通に注力してきました。しかし、「肩甲骨周囲筋だけを鍛えても、なかなか動きが改善しない…」と感じた経験はありませんか?
その答えは、運動連鎖(Kinetic Chain)の視点に隠されています。肩甲骨は、胸郭という不安定な土台の上に乗っています。そしてその胸郭は、骨盤や脊柱からなる「体幹(コア)」によって支えられているんです。つまり、体幹という土台が不安定では、その上にある肩甲骨が効率的に機能することは極めて難しくなります。
これまで、体幹の安定性が肩の機能に重要であることは指摘されてきましたが、SD患者さんに対して「体幹安定化エクササイズ(Core Stabilization Exercise: CSE)」を追加することが、具体的にどのような上乗せ効果をもたらすのかを検証した質の高い研究は多くありませんでした。
今回ご紹介するのは、まさにその疑問に答えてくれる最新のランダム化比較試験(RCT)です。この研究は、SDに対するリハビリテーションにおいて、なぜ局所的なアプローチだけでは不十分で、体幹からのアプローチが不可欠なのかを明確なエビデンスと共に示してくれています。
研究の核心:「体幹安定化エクササイズ」は従来のリハビリに何をもたらすか?
この研究では、SDと診断された80名の患者さんを2つのグループに分け、6週間の介入効果を比較しました。
-
対照群(従来法グループ) 温罨法やTENSといった物理療法に加え、振り子運動、壁を使った挙上運動、肩甲骨のプロトラクション/リトラクション、セラバンドを用いた内外旋運動など、肩関節周囲に焦点を当てた従来のエクササイズを実施しました。
-
実験群(体幹アプローチ追加グループ) 上記の従来法に加えて、体系的な「体幹安定化エクササイズ(CSE)」を実施しました。このプログラムは臨床でも応用しやすい段階的な負荷設定になっています。
-
Week 1-2: 腹式呼吸(Abdominal drawing-in)や骨盤ブリッジなど、低負荷で体幹の深層筋を活性化させることから開始します。
-
Week 3-4: 四つ這いでの対側上下肢挙上など、より動的な安定性が求められる課題へ移行します。
-
Week 5-6: スイスボール上での対側上下肢挙上やウォールスクワットなど、不安定な支持面でのエクササイズを取り入れ、さらに負荷を高めていきます。
-
この2群を比較することで、「体幹へのアプローチ」がもたらす純粋な上乗せ効果を検証したわけですね。
結果の深掘り:体幹の安定が肩甲骨周囲筋を“目覚めさせる”メカニズム
6週間の介入後、両群ともに痛み(VAS)や関節可動域(ROM)は改善しました。しかし、実験群(体幹アプローチ追加群)では、それを大きく上回る効果が確認されました。
1. 体幹の筋力(PBU)が圧倒的に改善 まず当然の結果として、CSEを実施した実験群では、圧力バイオフィードバック(PBU)で測定した体幹筋力が有意に向上しました。一方、従来法のみの対照群では、体幹筋力に有意な変化は見られませんでした。これは、従来型の肩関節リハビリだけでは、根本的な土台である体幹の安定性は改善されないことを示唆していますね。
2. 肩甲骨周囲筋の筋力(IMT)に驚くべき上乗せ効果 最も注目すべきは、体幹を鍛えた実験群の方が、肩甲骨周囲筋である前鋸筋(Serratus anterior)や僧帽筋下部線維(Lower Trapezius)の筋力も、対照群より有意に向上した点です。
なぜ、直接鍛えていない体幹のエクササイズが、肩甲骨の筋力をより高めるのでしょうか? 研究では、その理由を運動連鎖とフィードフォワード制御の観点から考察しています。体幹の筋群は、上肢を動かす際に先行して収縮し(フィードフォワード)、脊柱を安定させる役割を担います。CSEによってこの体幹の安定性が向上すると、肩甲骨周囲筋は過剰な固定作用から解放され、本来の役割である「上腕骨の動きに合わせた適切なポジショニング」に専念できるようになります。「安定した体幹」という最適な環境が整うことで、肩甲骨周囲筋の神経筋制御が改善し、結果として筋出力の向上に繋がったと考えられるわけです。これは、土台を固めることで、その上の構造物が効率よく働けるようになる、という力学的な原則そのものですね。
臨床応用:明日から使える「体幹×肩甲骨」統合リハビリテーションプログラム
この研究結果は、私たちの臨床に非常に重要な示唆を与えてくれます。
Step 1:評価の視点を変える まず、SD患者さんの評価において、肩甲骨の動きや筋力だけでなく、体幹の安定性も必ず評価項目に加えましょう。PBUがない施設でも、シングルレッグスタンスでの体幹の動揺や、ブリッジ動作時の骨盤の安定性など、簡易的に評価することは可能だと思います。
Step 2:介入プログラムを統合する 次に、リハビリプログラムの初期段階から、従来の肩甲骨エクササイズと並行して、低負荷のCSEを導入します。 例えば、以下のような段階的なプログラムが考えられます。
-
導入期(〜4週):
-
目的: 体幹深層筋の活性化と、肩甲骨の意識付け。
-
体幹Ex: 腹式呼吸、骨盤後傾運動、骨盤ブリッジ。
-
肩甲骨Ex: ウォールプッシュアップ・プラス、自動介助運動での肩甲骨後傾・上方回旋の誘導。
-
-
発展期(4〜8週):
-
目的: 動的な安定性の向上。
-
体幹Ex: 四つ這いでの対側上下肢挙上(バードドッグ)、サイドブリッジ。
-
肩甲骨Ex: セラバンドを用いたリトラクション、水平外転。
-
-
応用期(8週〜):
-
目的: 不安定な環境下での協調性向上と機能的動作への般化。
-
体幹Ex: スイスボール上での各種エクササイズ、ダイアゴナルパターン。
-
肩甲骨Ex: より高負荷でのバンドエクササイズ、プライオメトリクス(アスリートの場合)。
-
重要なのは、「安定した体幹の上で、肩甲骨を正しく動かす」というコンセプトをセラピストと患者さんが共有することです。常に体幹の安定を意識させながら肩甲骨のエクササイズを行うことで、両者の機能は相乗的に高まっていくはずです。
まとめ:リハビリのパラダイムシフト
今回の研究は、肩甲骨ジスキネジアの治療が、もはや肩関節周囲だけの問題ではないことを明確に示してくれました。体幹安定化エクササイズは、単なる「追加の運動」ではなく、肩甲骨の機能を最大限に引き出すための「必須の土台作り」であると言えるでしょう。
痛みや筋機能、そして運動制御。これら全てを改善するために、明日からの臨床でぜひ「体幹と肩甲骨の統合」という視点を取り入れてみてください。きっと、これまで伸び悩んでいた患者さんの機能回復に、新たな突破口が開けるはずです。
